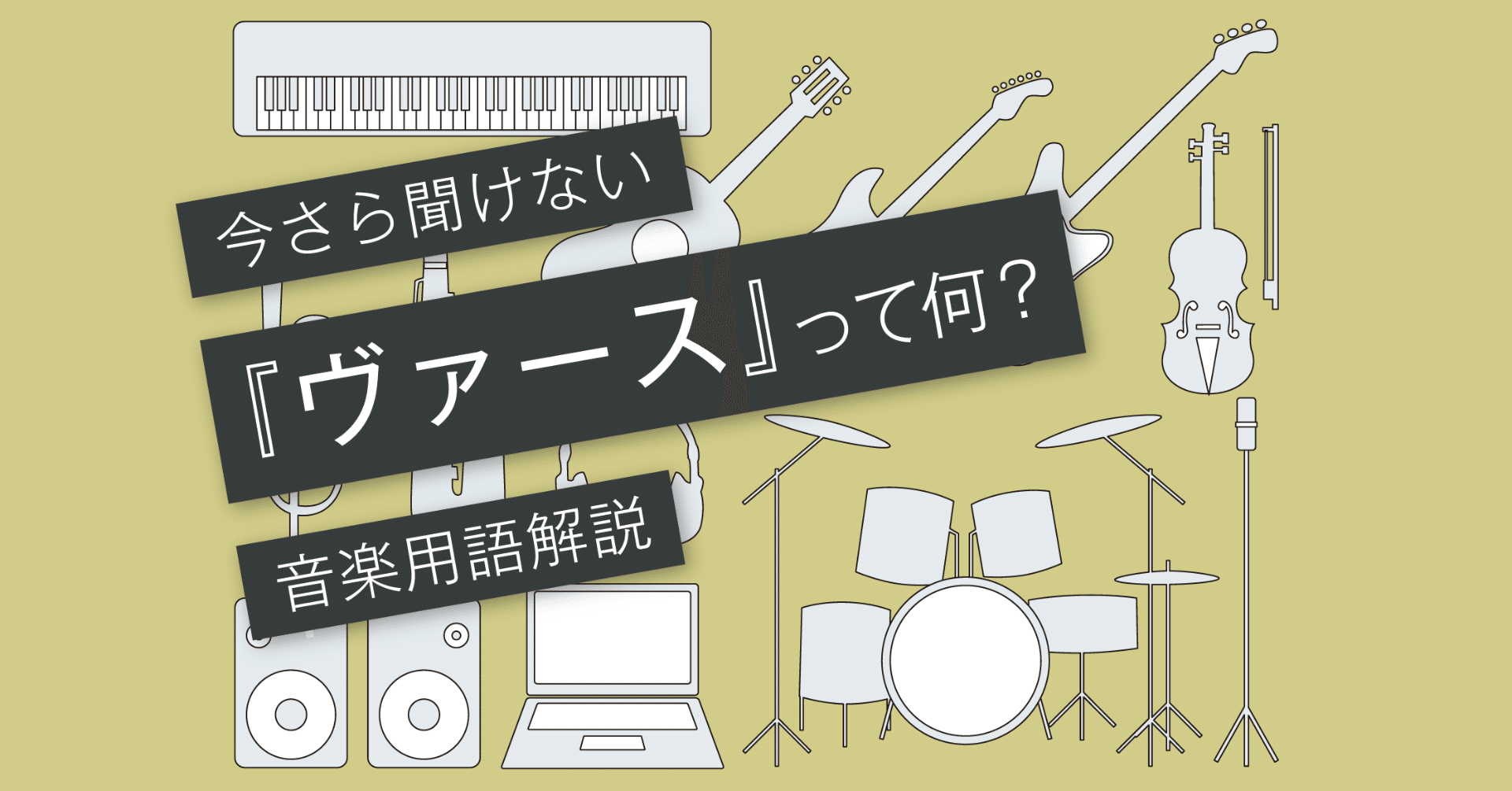間奏曲(かんそうきょく)は、間に演奏する経過的な楽曲(普通は器楽曲)の総称。 インテルメッツォ(独: Intermezzo)、インテルメッゾ(伊: intermezzo)と呼ばれるものにほぼ相当する。長い出し物のセクションの間に演じられる短いショー(音楽やダンスなど) の意
- 幕間
- 合の手
- 間奏曲
- あいの手
- 相の手
- 間の手
奏でる/奏する/弾く の類語 – 日本語ワードネット
- 演技
- 実演
- 出演
- 上演
- 弾く
- 演奏
- 演じる
- 演ずる
「間奏」の例文は?「間奏」の例文・使い方・用例・文例
- 間奏を演奏する
- 美しいアドリブで間奏を演奏したギター・プレーヤー
- 邦楽で,手事という間奏部分
- 地唄や箏曲で,長い間奏に入る前の唄の部分
音楽用語で幻想曲とは何ですか?
形式にとらわれず、楽想のおもむくままに作られた器楽曲。 即興的性格の強いもの(J.S. バッハ〈半音階的幻想曲とフーガ〉)もある。 ロマン派では、幻想的夢想的な性格を持つ小品を指し、シューベルト〈さすらい人幻想曲〉、ショパン、シューマンの作品などがある。プレリュードともいう。 作曲者によっていろいろな使われ方がされており,形式も 比較的 ひかくてき 自由である。
曲の終わりを何というか?
アウトロ(英: Outro)は、音楽用語であり、楽曲の終わりの部分を指す略式の表現である。
複数人でひとつの楽曲を一緒に演奏すること
- コンボ演奏
- 二重奏
- 連弾
- アンサンブル
- 大合奏
- ブラスバンド演奏
- 合奏
- 重奏
「奏」の別の言い方は?
かなでる すすめる
- ①すすめる。 たてまつる。 申しあげる。「
- 演奏(エンソウ)・合奏(ガッソウ)・協奏(キョウソウ)・上奏(ジョウソウ)・序奏(ジョソウ)・吹奏(スイソウ)・前奏(ゼンソウ)・弾奏(ダンソウ)・独奏(ドクソウ)・伴奏(バンソウ)
- 出典『角川新字源 改訂新版』(KADOKAWA) 会意。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「器楽」の意味・わかりやすい解説
声楽の対語で、楽器のみで演奏される音楽の総称。 演奏形態から独奏と合奏とに大別されるが、各演奏者が対等な合奏は重奏とよばれることが多い。 また管弦楽は多種類の楽器を用いた多人数による合奏である。ビジネスメールなどでの「何卒」の使い方と例文
- 「何卒よろしくお願いいたします」
- 「なにとぞ倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます」
- 「何卒ご了承ください」
- 「何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます」
- 「何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」
- 依頼の理由を添えてから使う
「狂詩曲(きょうしきょく)またはラプソディ(英: rhapsody、独: Rhapsodie、仏: rhapsodie、伊: rapsodia)は、自由奔放な形式で民族的または叙事的な内容を表現した楽曲。 異なる曲調をメドレーのようにつなげたり、既成のメロディを引用したりすることが多い」(ウィキペディアより)。
音楽用語で「(♮)」とは何ですか?臨時記号の仲間に♮(ナチュラル)、×(ダブルシャープ)、♭♭(ダブルフラット)などがあります。 それぞれ、音の上下のリセット、半音2つ分上げる、半音2つ分下げるの意味があります。
プレリュード曲とはどういう意味ですか?音楽用語ダス 「プレリュード」の解説
前奏曲。 もともとは歌劇など曲のはじめに演奏される曲のことであったが、ショパンやスクリャービン、ドビュッシーに代表される作曲者によって、独立した様式の曲として広まっていった。
即興曲は別名何といいますか?
アンプロンプチュともよばれる器楽小品。 とくにロマン派のピアノ曲に多い。 19世紀以前には幕間劇や特殊なカノンを意味していた。 しかし、今日のような意味での即興曲という表題は、1817年にチェコの作曲家ボルシジェクJan Hugo Voříšek(1791―1825)が最初に用いたといわれる。
こうそう‐きょく【後奏曲】
〘名〙 (postlude, Nachspiel の訳語) 教会で、礼拝終了後、会衆が退場するときに演奏されるオルガン曲。 また、コーダのこと。しゅう‐きょく【終曲】
交響曲・協奏曲・組曲など、多楽章形式の楽曲の最終楽章。合奏の類語・言い換え・同義語
- コンボ演奏
- 二重奏
- 連弾
- アンサンブル
- 大合奏
- ブラスバンド演奏
- 合奏
- 重奏