
状態量ジョウタイリョウ
たとえば,温度,圧力,体積,内部エネルギー,エンタルピー,エントロピー,ギブズエネルギーなど. これらの量はいかなる過程を経てその状態に到達したかには無関係である.エントロピーとは物理学の言葉で、日本語では”乱雑さ”を意味します。 秩序あるものは、秩序がなくなる方向にしか動かない、という宇宙の大原則のことです。まず、「エントロピー」とは「無秩序の度合いを示す物理量」です。 具体例で言うと 「部屋が片付いている状態」(秩序ある状態)→エントロピーが小さい 「部屋が散らかっている状態」(無秩序な状態)→エントロピーが大きい ということです。 つまり、無秩序であればあるほどエントロピーの値は大きくなる。
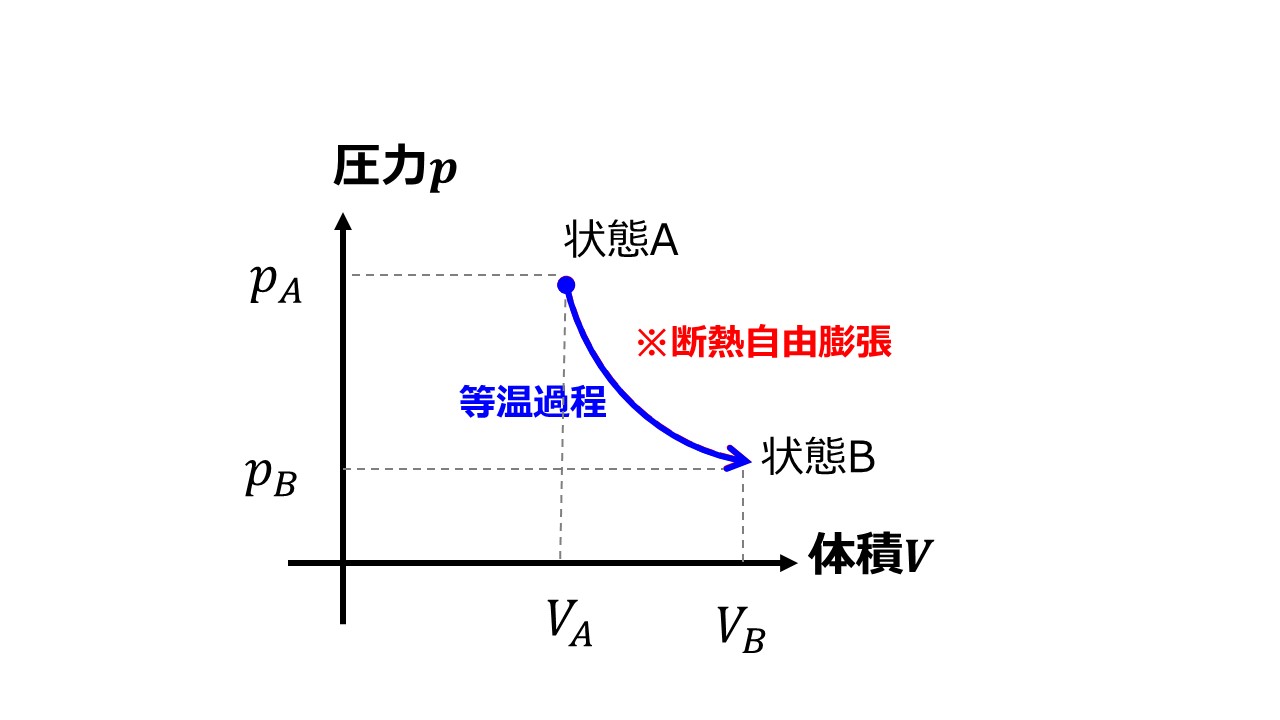
エントロピーが減少するのはどれか?物質やエネルギーの乱雑さが増大すればエントロピーは増大し、乱雑さが減少すればエントロピーは減少する。
動力は状態量ですか?
圧力、温度、体積のようにある物質の状態を表すものを状態量と言います。 この他にエンタルピー、エントロピー、内部エネルギーなど色々な状態量があります。 状態変化によって発生するもの、例えば熱量、動力、仕事 等は状態量ではありません。エンタルピー(英: enthalpy)とは、熱力学における示量性状態量のひとつである。 熱含量(ねつがんりょう、英: heat content)とも。 エンタルピーはエネルギーの次元をもち、物質の発熱・吸熱挙動にかかわる状態量である。
エントロピーとは簡単に言うと何ですか?
「無秩序な状態の度合い(=乱雑さ)」を定量的に表す概念で、無秩序なほどその値が高く、秩序が保たれているほど低い値となる。 例えば、教室の中できちんと座っている幼稚園児の状態の「エントロピーは低い」と表し、休み時間に園庭を思い思いに楽しそうに走り回る園児たちの状態の「エントロピーは高い」と表します。
全体としてエントロピーは増大しているが、局所的に低いエントロピーが実現されている。 身近な例として、エアコンや冷蔵庫が挙げられる。 冷却装置によって部屋の温度が外より下がっている状態は、ほうっておけば外から熱が流れ込んで、やがて温度が等しくなってしまう。 つまり、温度差がある状態はエントロピーが低い状態である。
エントロピーが増大する例は?
これは日常的にもよく目にする現象で、例えば以下のような例があります。
- 拡散した気体は元に戻らない
- 常温に置かれた熱湯は自然に冷めるが、一度冷めた水が勝手に熱湯に戻ることはない
- コーヒーにミルクを入れると自然に混ざるが、勝手に分かれることはない
- 覆水盆に返らず
状態量:状態に応じて決まる物理量。 または物体の状態を表す物理量ともいえる。 温度T、圧力Pなど。 非状態量:状態を指定しても定まらず、状態変化の経路(仕方)にも依存する物理量。エンタルピー:熱の外部へのはたらきによる損失分を取り込んでいる状態量。 ⇒ 仕事のことは考えず、熱だけで状態を表すことができる関数。 減ったり増えたりする。 エントロピー:乱雑さを表す状態量。

水が貯まった樽は、値段が高く、エンタルピーも高い。 水があまり入っていない樽は、値段が安く、エンタルピーも低い。 つまり、「エントロピー」は、脂肪が散らばった「トロ」から「乱雑さ」を、「エンタルピー」は、水が貯まる「樽」から「エネルギー」をイメージします。
エントロピーが高いものは何ですか?エントロピーが高いものは具体的には廃棄物や廃熱などであり、こうした不要物が地球上に増えていく。 これは「エントロピー増大の法則(熱力学の第二法則)」と呼ばれ、絶対的な物理法則である。 資源もこの法則に従い、一方向に拡散し劣化する。 その逆に濃縮し質を高めるには、エネルギーの投入が必要になる。
エントロピーが増加する例は?これは日常的にもよく目にする現象で、例えば以下のような例があります。
- 拡散した気体は元に戻らない
- 常温に置かれた熱湯は自然に冷めるが、一度冷めた水が勝手に熱湯に戻ることはない
- コーヒーにミルクを入れると自然に混ざるが、勝手に分かれることはない
- 覆水盆に返らず



