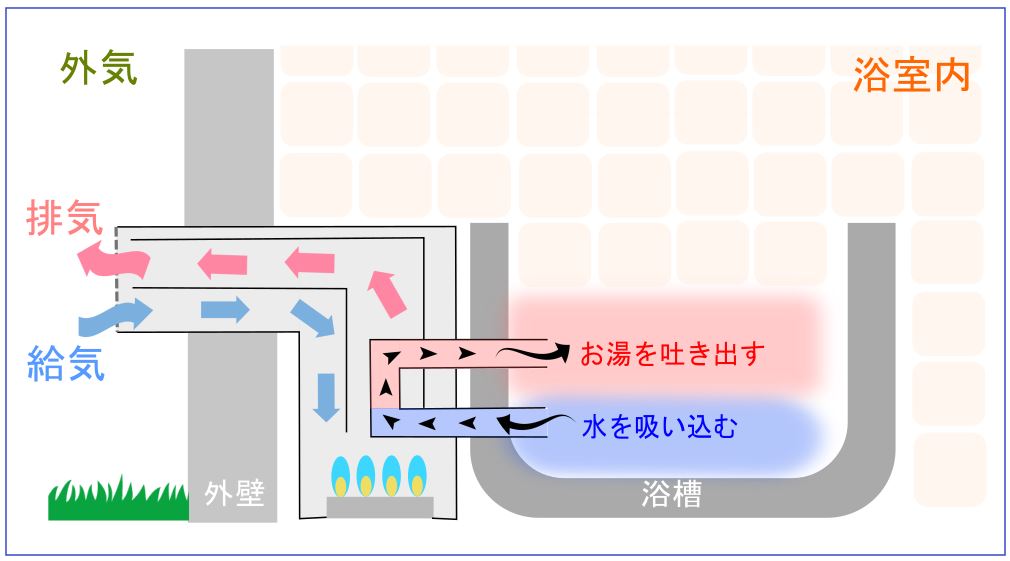日本語では「湯船」と似た言葉に「浴槽」がありますが、英語では「バスタブ」という一語で表現され、他に変わる言葉はありません。「湯船」は江戸時代に使われていた言葉ですが、それ以前にも浴槽を指す言葉として、「ゆぶね」が使われていました。「入浴」は、風呂に入ることの一般的な言い方。 「湯あみ」は、古風な言い方。
「湯舟」の言い換えは?湯船 の類語
- 風呂桶
- 湯槽
- バスタブ
- 湯ぶね
- 湯桁
- バス
- 浴槽
バスタブの和訳は?
湯船/浴槽/風呂桶/バスタブ の共通する意味
湯を入れて、人がその中で入浴する桶や箱。浴槽の事をいいます。 英名が「バスタブ」。 一般的な素材はFRPやホーロー、ステンレスが多く、高級バスタブには人造大理石やタイルなどをあしらったタイプもあります。 サイズは肩までお湯につかれる深めのタイプや、足を伸ばせる長細いタイプ、その中間のタイプが主なものです。
浴槽の正式名称は?
バスタブとは、浴槽のこと。 座って肩までお湯につかれる和風タイプ、体を横たえて入浴する広く浅い洋風タイプ、その中間である和洋折衷タイプなどがある。
浴槽とは、浴室の中でお湯を溜めて浸かるための容器のこと。 別名、風呂桶、湯船、バスタブともいう。 素材は、FRP樹脂や人造大理石が主流のほかに木製やステンレス、ホーローなどもあります。
お風呂 湯船 なんていう?
1. 浴槽(バスタブ) 皆さんご存知の浴槽(バスタブ)です。お‐ゆ【御湯】 〘名〙 (「お」は接頭語) 「湯」の尊敬・丁寧語。 ① あたたかい水。 特に、お風呂。ちなみに、湯舟と湯船では特に意味の違いはないらしく、一般的なのは湯船の方らしい。 舟と船では、「舟=小型で手漕ぎなもの」「船=大型で動力があるもの」と多少の違いがあるらしく、ただお湯を張るためだけのゆぶねはどちらかといえば湯舟なのではとも思うが、昨今の機能豊富なゆぶねを想像すると湯船なのかも。
1 入浴用の湯を入れ、人がその中に入る大きな箱または桶。 浴槽。 2 江戸時代、船内に浴槽を設け、停泊中の船を回り、料金を取って船乗りや客を入浴させた船。
お風呂の呼び名にはどのようなものがありますか?風呂/風呂場/浴室/バス/バスルーム/湯殿 の使い分け
「風呂」は、最も広く用いられる。 入浴のための設備、場所ばかりでなく、「風呂に入る」「風呂をわかす」のように、浴槽や、その中の湯の意でも用いられる。 「風呂場」「浴室」は、入浴するための場所。 「浴室」の方が書き言葉的な語。
お風呂の湯船の名前は?1. 浴槽(バスタブ) 皆さんご存知の浴槽(バスタブ)です。
お風呂のバケツの名前は?
お風呂に欠かせないバスグッズである湯おけ。 風呂おけ・手おけ・洗面器など呼び方は違えど、どのご家庭にも1つはあるのではないでしょうか?
風呂/風呂場/浴室/バス/バスルーム/湯殿 の使い分け
「風呂」は、最も広く用いられる。 入浴のための設備、場所ばかりでなく、「風呂に入る」「風呂をわかす」のように、浴槽や、その中の湯の意でも用いられる。 「風呂場」「浴室」は、入浴するための場所。 「浴室」の方が書き言葉的な語。浴槽。 英語のbathtub。 もともと独立した家具であったが、最近はユニットバスに組み入れられている。ちなみに、湯舟と湯船では特に意味の違いはないらしく、一般的なのは湯船の方らしい。 舟と船では、「舟=小型で手漕ぎなもの」「船=大型で動力があるもの」と多少の違いがあるらしく、ただお湯を張るためだけのゆぶねはどちらかといえば湯舟なのではとも思うが、昨今の機能豊富なゆぶねを想像すると湯船なのかも。