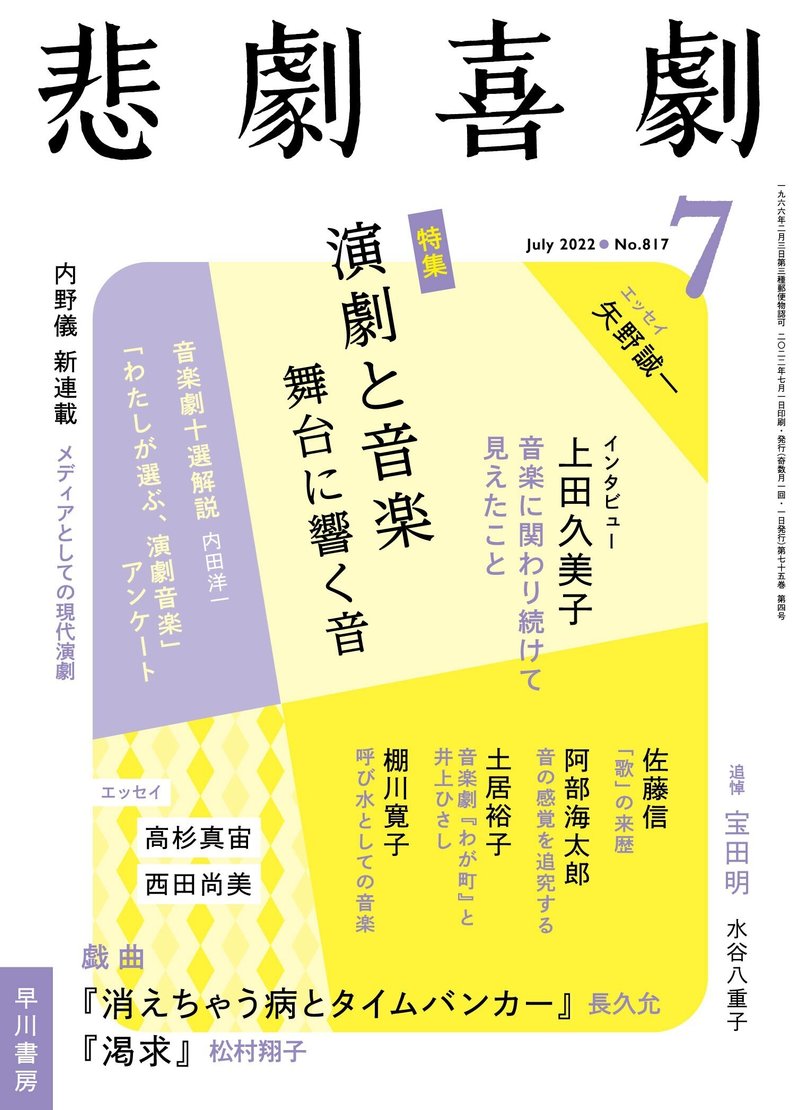音楽伴奏つきの芝居 「メロドラマ」はギリシア語の「歌(メロス mélos)」と「劇(ドラマ drama)」の合成語で、とくに18世紀のフランスとドイツで上演されていた演劇形態のひとつを意味していた。「メロドラマ」( melodrama )は、「mēlos」と「劇」の意味の「drāma」が合成された語で、演劇形式の一つ。 「誇張された状況設定やせりふをもつ通俗的な演劇。 ヨーロッパで、中世から近世に行われ、せりふの合間に音楽を伴奏した娯楽劇」(精選版・日本国語大辞典)。広辞苑によると、メロドラマとは「波乱に富む感傷的な通俗恋愛劇。 18世紀イタリアに起こった、音楽を伴奏としてせりふの朗誦を行う劇」とある。 簡単に言えば、感情の起伏が激しい愛憎劇だ。 「メロ」とはギリシャ語で「歌」を意味する。
メロドラマティックとはどういう意味ですか?メロドラマ【melodrama】
今日では、恋愛を主なテーマとした通俗的、感傷的な演劇・映画・テレビドラマなどをいう。
日本のメロドラマの代表作は?
戦前の「愛染かつら」と並ぶ“スレ違いメロドラマ“の代表作。 原作は1952年からNHKで放送された菊田一夫のラジオドラマ。メロドラマの一般的解釈とは、辞書によりますと「19世紀初期にイタリアやフランスで流行した、音楽(メロディー)入りのロマンティックな通俗劇」とあるように、メロディーとドラマを合わせた非常に通俗的なものです。
「妻」の意味と由来は?
中国語で「一家の主(あるじ)」が語 源とされ、上下関係・主従関係の意 味があるようです。 「男人(をひと)」から変化して「おっ と」になった言葉とされ、妻から見 た配偶者を指しています。 もともと「つま」は男女にかかわら ず配偶者や恋人を指していたようで す。 「夫」と書いて「つま」とも読ん でいました。
「嫁(よめ)」は本来息子の配偶者に使う言葉
「嫁」は「嫁ぐ」とも読める通り本来は息子の配偶者に対する呼び方で、対義語は「婿」。 これに加えて自分の妻や他人の妻を呼ぶ意味でも古くから使われているため、自分の配偶者を嫁と呼ぶのも間違いではないようです。
「恋愛劇」の言い換えは?
メロドラマ(melodrama)
今日では、恋愛を主なテーマとした通俗的、感傷的な演劇・映画・テレビドラマなどをいう。「愛情の裏返し」とは、好きな人にあえて嫌がることをしたり冷たくすることを意味します。 一般的に好きな人に対しては、褒めたり優しくしたりしますよね。 しかし、このような愛情表現とは正反対な行動にでてしまうのが、愛情の裏返しです。[補説]meroは、スペイン語でスズキ目ハタ科の食用魚を総称する語。
「dramatic」の基本的な意味
「dramatic」とは「劇的な」「戯曲の」「演劇の」を意味するほか、「めざましい」「芝居がかった」「印象的な」「大袈裟な」などを表わす。 「dramatic」の品詞は形容詞だが、名詞として使う場合は「drama」を用いる。
メロドラマ いつから?18世紀の後半フランスに生れ,19世紀に欧米で流行した演劇の一形態。
メロドラマの特徴は?メロドラマとは、善悪の葛藤のような明確な二項対立を中心に物語が展開し、主人 公は犠牲者となってたくさんの災難と苦悩を経験するが、最終的には救われる。 こ の単純な道徳性を盛り上げる、大げさな身振りや誇張されたセットなど、しばしば 象徴性と隠喩に満ちたミザンセーヌを表現上の特徴とする。
奥さんの呼び方はダメですか?
結論からいうと、正しいとされている呼び方は「妻」です。 「奥さん」や「嫁」は、ご自身の配偶者のことを指す呼称としては正しくありません。
「家内」の意味は、
この「家の中」という言葉が、次第に「家の中にいる女性」を表すようになっていくわけですが、広く「妻」のことを「家内」と呼ぶようになったのは、明治時代になってからのことでした。 男性が外で働き、女性は専業主婦として家の中で家事を行うという家庭のスタイルが生まれた時代です。【配偶者(女性)をさす表現】
| 妻 | 「配偶者である女性」を意味する言葉 |
|---|---|
| 嫁 | 妻。または、他人の妻をいう言葉 結婚して、夫の家族の一員となった女性 息子の妻となる女性 |
| 家内 | 妻。通常、他人に対して自分の妻をいうときに用いる 家の中。屋内 家族 |
| 女房 | 妻のこと。多く、夫が自分の妻をさしていう言葉 貴族の家に仕える侍女(小間使い) |
プラトニックラブ(プラトニックラヴ)とは、肉体関係のない恋愛そのものや恋愛関係を指し、「プラトニック」と同様の意味で使われることが多い。