
このように同じ部分を持ち、同じ音で読む漢字を形声文字と言います。同類/同種/同系 の共通する意味
同じグループに属すること。 また、同じ仲間。訓読みは同じでも、漢字が異なるものを「同訓異字」と言います。 逆に「回」、「会」、「開」のように、音読みが同じ読み方で漢字が異なるものを「同音異字」と言います。 音読みが同じでも意味の違う二つ以上の漢字の場合は「同音異義語」、形は似ていても異なる漢字は、「似形異字」と言います。

「同」に似た感じの漢字は?た行 ー と
- ①おなじ。 ひとしい。「 同一」「同様」 異 ②ともに。
- 一同(イチドウ)・異同(イドウ)・共同(キョウドウ)・協同(キョウドウ)・合同(ゴウドウ)・混同(コンドウ)・賛同(サンドウ)・帯同(タイドウ)・不同(フドウ)・雷同(ライドウ)
- 出典『角川新字源 改訂新版』(KADOKAWA) 会意。
同じ音で違う漢字は?
同音異字(どうおんいじ)とは、同じ音の語や字でありながら、別の文字であること。 通常の熟語のほか、伊東と伊藤(いとう)、東海林と庄司(しょうじ)、仙台(宮城県)と川内(鹿児島県)(せんだい)のように、人名や地名でも見られる。 ここでの「音」の意味は「発音」の意味で、「音読み・訓読み」の「音」ではない。同じ音をもつが,字としては 異 こと なる漢字のこと。
辛いと辛いは同じ漢字ですか?
「からい」と「つらい」が同じ漢字を用いるのは、そもそも「からい」が味覚の一種ではないためです。 味覚には「辛味(からみ)」は含まれていません。 実際、人間の舌が感じる辛さは、味覚ではなく「痛覚」の一部とされています。 この痛覚は、要するに「痛み」として感じられるものです。

「惚れる」と「惚ける」であるが、両方同じ漢字であり、送り仮名によって読み方が変わるのである。
同じ読み方でちがう漢字を何といいますか?
同じ漢字なのに、読み方と意味が違う字を「同字異音」と言うぞ。 たとえば「声明」と書いて「せいめい」と読めば自分の立場や考えをはっきりと表明することだが、「しょうみょう」なら仏教で独特の節をつけて経文を読むことになる。 「黒子」を「くろご」と読めば歌舞伎などで黒い衣装を着ている人だが、「ほくろ」とも読むんだよ。同音異義語の例を挙げると、きこう(機構、気候、寄稿など)、かんしょう(鑑賞、観賞、干渉など)、しじょう(市場、史上、誌上など)、たいせい(体制、耐性、態勢など)、ほしょう(保証、保障、補償など)などがあります。同音異義語とは、読んで字のごとく「音は同じだけど意味が違う言葉」のことです。 日本語だと、「柿」と「牡蠣」や、「橋」と「箸」などですね。
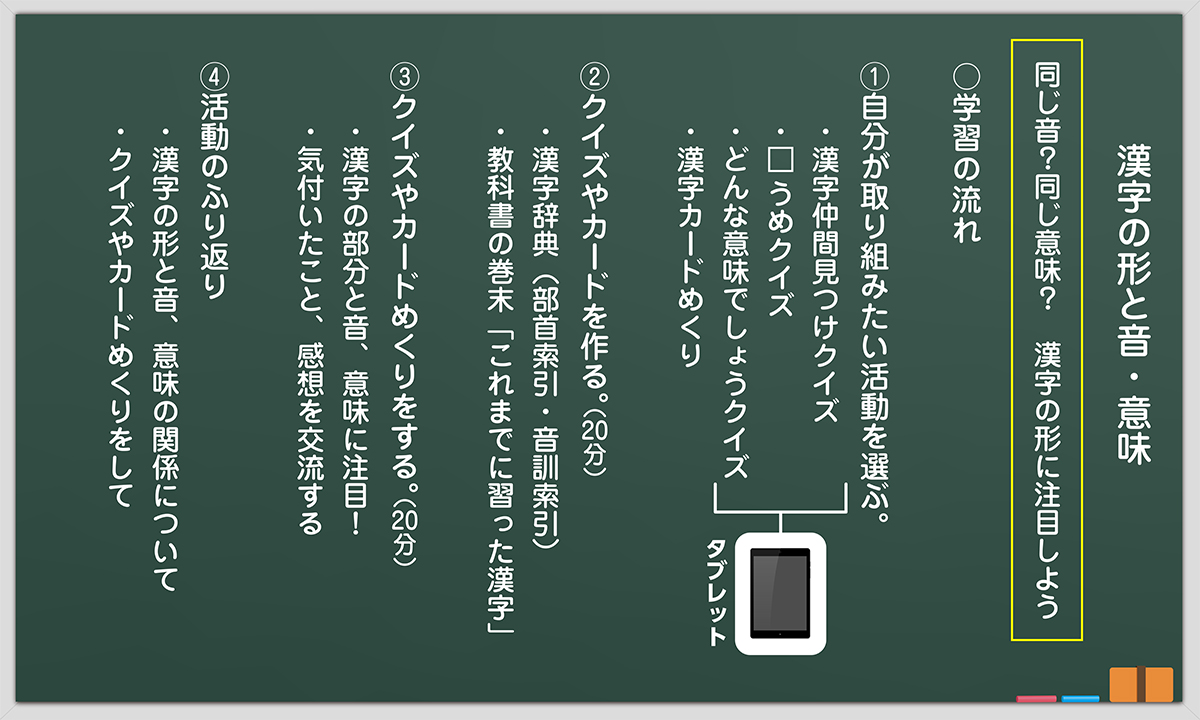
同音異字の例
- 偏在 – 遍在(正反対となる)
- 冷遇 – 礼遇(正反対となる)
- 競演 – 協演(正反対となる)
- 賦活 – 不活(正反対となる)
- 売春 – 買春(正反対となる)
- 犯す – 侵す – 冒す
- 強行 – 強攻 – 強硬
- 即効 – 速効 – 速攻 – 即行
同じ読みでも意味が違う熟語は?「読み方は同じだけど,意味が違う熟語」を「同音異義語」「同訓異義語」といいます。
「惚れる」と「惚ける」は同じ字ですか?「惚れる」と「惚ける」であるが、両方同じ漢字であり、送り仮名によって読み方が変わるのである。
「つらい」の漢字は?
「からい」も「つらい」も漢字は「辛い」ですね。 文字にしたときは、その内容から、どう読むかを判断するしかありませんが、新聞などでは、原則、「つらい」は、平仮名にして書き分けます。 国が定めた「漢字使用の目安」である常用漢字表では、「辛い」の訓読みは「からい」しかないためです。

この漢字、なんて読むか分かりますか 普通に読むと「ぼける」「ほうける」などになりますが、別の読み方もあるんです!では正解を確認していきましょう。 この「惚ける」という漢字は「とぼける」と読みますよ。 「惚ける」とは、わざと知らないふりをすることを意味しています。同音異義語の例を挙げると、きこう(機構、気候、寄稿など)、かんしょう(鑑賞、観賞、干渉など)、しじょう(市場、史上、誌上など)、たいせい(体制、耐性、態勢など)、ほしょう(保証、保障、補償など)などがあります。隹二つと、又(ゆう)(て)とから成る。 隹一つが一羽の鳥を手に持つのに対して、二羽の鳥を手で持つことから、一つがいの鳥の意。 転じて、対になるものの意に用いる。



